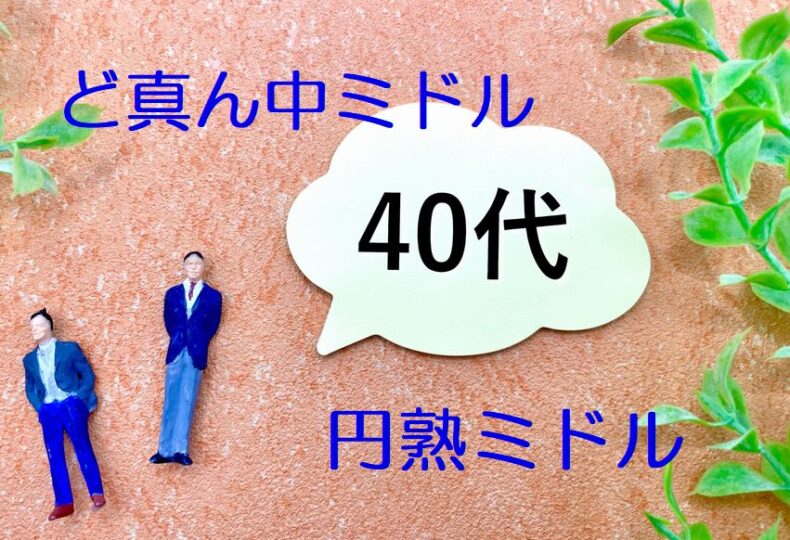
ミドル転職・中年フリーターの現実から考える副業・起業という選択肢
今月2025年5月1日にリスタートした当サイト「副業起業.com」。
その基本的な視点は、「すべての人に副業起業の機会が」というものです。
そうした意識を、ここまで投稿した以下の4つの記事を通じて、お伝えしてきました。
・新しい働き方を模索するあなたへ|副業・起業時代のWEB発信 – 副業起業.com
・副業から起業へ!独立を目指すあなたに伝えたい6つの視点と行動指針 – 副業起業.com
・副業市場は今どうなっている?統計に現れない働き方の実態と可能性 – 副業起業.com
・新しい時代の働き方と人生設計|コロナ・災害・AI時代を生き抜く副業と起業の選択肢 – 副業起業.com
今回と次回の2回は、「すべての人」を具体的に絞って、その可能性と現実性を確認してみたいと思います。
ページに広告が含まれる場合があります。
ミドル世代の転職増加が提起する「専門性」の在り方と副業起業
10年前2015年のミドル世代の雇用市場事情から
今回は、「ミドル世代」に焦点を当てます。
恐縮ですが、今から10年前のミドルの労働市場・雇用状況を取り上げた、3つの記事を参考に話を進めます
エン・ジャパンの転職サイト「ミドルの転職」から分かるミドルの立ち位置
初めは、2015/10/6付日経の<ミドルの転職「増えた」45% >というダイジェスト記事から
-----------------------
人材サービスのエン・ジャパンが転職サイトの利用者約550人を対象に7月末~8月末実施のアンケート調査。
30代後半から50代前半の7割以上が自分をミドル世代だと考えていた。
45%はミドル世代の転職が増えていると感じると回答。
これまで転職といえば20代後半~30代前半が中心だったが、徐々に上の年代にも広がっていることを示している。
転職活動をする上でぶつかる壁については、72%が「年齢」を挙げ、「年収・給与」が41%と続いた。
------------------------
ミドルにもある種類、階層|駆け出し・ど真ん中・円熟ミドル
同社には、ミドルの可能性を拡げるとして、「ミドルの転職」事業サイトがあります。
ミドルとは、どの年代を指すのでしょうか?
・「30代前半、駆け出しミドル」
・「30代後半、ど真ん中ミドル」
・「40代、円熟ミドル」
という表現がこのサイトで見られます。
この枠から外れる50代は、ミドル枠から外れることになりますね。
エグゼクティブ・クラスではない50代での転職は、厳しいということでしょうか。
アンケートでは、50代前半組にも、自分をミドルと考える人もいたのですが。
別のアンケートでは、50歳代以上では、シニア層、中間管理層、中年層と定義することを選択する人が多数、と
65歳定年制の企業が普通になり、高齢者も減少する生産年齢人口をカバーするための貴重な?資源とされれれば、ミドルにとっては逆に閉塞感を感じされられることにもなるわけで。
となると転職も一つの選択肢として十分考える背景となり、その価値もまだ十分にある。
同サイトでは、企業によるミドル採用理由としてまず「マネジメント力・組織力の強化」。かつ「業界知識・経験」と「問題意識を基にした課題設定力」を重視していると。
成長段階にある企業での舵取りを任せられるポジション人材へのニーズを示しています。
同じミドルでも、駆け出しと円熟では、随分違いに幅があると思うのですが。
エン・ジャパンの「ミドルの転職」を用いた転職事情・雇用動向は、その後も、日経で頻繁に取り上げています。
以下、記事例とその要約を。
エン・ジャパン「ミドルの転職」調査|コロナ禍での35~59歳ミドル世代の転職意識の変化
一つ目は、以下の記事。
要約を添えました。
⇒ ミドル世代、55%がコロナで転職意欲高まる – 日本経済新聞(2021/7/16)
・転職意欲の高まり(35~59歳ミドル世代)
コロナ禍を機にミドル世代の55%、特に50代では61%が転職意欲を強めた。
・転職理由
主な理由は「業界の将来不安」と「成長実感の欠如」で、ともに30~50代で36%。
・働き方への不満と期待
働き方に変化がなかった人の71%が不満を抱き、「リモートワーク」や「時差出勤」など柔軟な制度を求めている。
エン・ジャパン「ミドルの転職」利用の2022年ミドル女性転職事情
もう一つ、次の日経記事の要約を。
⇒ ミドル女性の転職年収上昇 対話力、ロールモデルに期待 – 日本経済新聞(2023/3/15)
・ミドル女性の転職年収の上昇
2022年の40代女性の転職年収中央値は590万円、50代女性は647万円で、いずれもコロナ前より上昇。
・「35歳転職限界説」の変化
かつての「35歳限界説」は崩れつつあり、年齢や性別にとらわれず採用する動きが広がっている。
・企業の採用姿勢の変化
企業は人手不足や定年延長を背景に、職務遂行力や長期雇用への期待を重視し、ミドル世代女性の転職機会が拡大。
ミドル世代の副業・起業をススメルための記事ですが、初めに、転職市場について紹介しました。
保育・介護にも対応できるワーク・アンド・ライフのための副業起業
話しを転じて、1950年生まれの私は、ど真ん中ミドルの30代後半での転職と起業独立、両方を経験しました。
まだ旧き良き昭和の時代だったから、と言えるでしょうか。
平成は、非正規雇用から正規雇用に切り替わることを期待することが非常に難しかった時代。
し化し、令和の時代に入り、一部の業種・職種では人材不足・人手不足を理由に、非正規雇用者を正規雇用に切り替える動きが、活発化しています。一部の大手企業やITk系企業に限ったもので、中小・零細企業や地方企業ではまだまだですが。
子育てや介護と仕事との両立も、常に生活と仕事上のリスク要因、困難な要因となる時代。
その中で、賃金・収入のアップも伴った転職は、上記の経営管理能力を含むIT等高度な専門能力を持つわずかの人に限られるように思えます。
しかし考え方を変え、見方を変えると、これからの時代における専門性とは、どういうものか?
企業サイドが求めるものとは別に、個人が自分の興味関心・好奇心をベースに、「こだわり」を持って時間を注ぎ込む領域と対象が「専門」ではないかと。
そう思うのです。
その専門性をビジネス化することで独立し、あるいは、半就労・半独立の状態を創り出し、仕事と生活(ワーク・アンド・ライフ)にも対応できるような働き方・生き方を設計する。
半就労・半独立状態も選択肢として十分、あり、です。
このような状態で、副業に取り組んでいる状況をイメージできますか。
駆け出しミドル、ど真ん中ミドル、円熟ミドル|駆け出しシニア、ど真ん中シニアにも参加の権利
どのミドルでも、副業を考えてみる価値はある気がします。
もちろん、超円熟の50代ミドル、60代の駆け出しシニア、70代のど真ん中シニアも十分参加する権利はあります。
単純に年代・世代軸で考えるのではなく、個々人のライフステージの状況により、意欲により、そしてスキルにより、ニーズも可能性もあります。もちろん取り組む仕事内容にも違いがあることは当然ですが。

増える中年フリーター、消えるフリーター?|働き方の多様化が可能にする人生再設計
若年フリーターと中年フリーターの動向|2015年毎日新聞レポートから
次も、同年2015年08月04日付毎日新聞記事から。
非正規雇用労働者数が、1990年代前半のバブル崩壊後、経済が長期停滞した「失われた20年」に右肩上がりに増加。
2015年1〜3月期平均で1979万人で、労働者全体の37.7%。
34歳までの「若年フリーター」はピークの03年からは減少。
一方90年代後半からの「就職氷河期」に遭遇した世代を含む35歳以上「中年フリーター」は増加に歯止めがかかっていない。
「中年フリーター」とは、35〜54歳の非正規の職員・従業員(除く女性既婚者)
90年代の130万人台での安定期から、バブル崩壊後約10年経過の2000年代以降の増加傾向が顕著で、15年には273万人に。
主婦パート中心の非正規雇用が、企業の雇用政策の変化もあり、主要な稼ぎ手であっても契約社員・派遣社員に切り替えられ増加してきている。
毎日新聞による中年フリーター対策の無責任論点
同紙の論述を整理すると。
1)非正規問題について
賃金を一律に上げるのではなく、それぞれの仕事に見合った対価を支払う必要がある。景気が悪くなったら突然クビを切るような不安定さは問題。
2)中年フリーターについて
長期的に同じ仕事を続けてきたなら、その技術を生かせるマッチングの機会を増やすなどの対応ができると思う。労働者側の意欲も大事。
3)非正規雇用労働者について
どこかに決着の地点があると思ったが、10年たってもまったくない。10年前は若者の貧困だったが、今はもう若者じゃない。中年になり、それがどんどん初老になり、高齢者になっていく。
まとめると、「年金・保険などセーフティーネットの強化や正社員への転換を後押しする制度作りなどに社会全体で取り組む姿勢が求められている」と、いとも簡単に結んでいます。
なんとも無責任な話で、現実的にイメージしにくいですね。
<社会全体>で取り組むとは、どういう取り組みか。
意欲や姿勢があればどうにかなるという類のものでは、まったくありえない。
労働者派遣法改正やアベノミクス第2弾をもってしても、非正規社員が正規社員にどんどん変わるなどという保障(保証)も現実も、恐らくありえない。
フリーターがいなくなる?
前項のミドル視点課題と同様、「中年フリーター」をテーマとした日経記事を2つ紹介します。
中年フリーターの実像
一つ目は、以下の記事の中の「中年フリーター」についての要約。
⇒ 企業と就活生 続く化かし合い – 日本経済新聞(2018/4/21)
中年フリーターは近年増加傾向にあり、特に25~54歳の非正規雇用の男性が増加。若者や主婦と比べ、不本意ながら非正規で働き続けるケースが多いのが特徴。(総務省労働力調査)
35~54歳中年フリーターは2002年以降の10年間に258万人から364万人へ106万人増加。(内閣府試算)
消える用語「フリーター」|働き方の多様化が要因?
もう一つは、以下の記事で、その要約も。
⇒ フリーター、立場一転(平成って) – 日本経済新聞(2019/4/18)
・フリーターの誕生と変遷
1980年代末に「夢を追う若者」の象徴として登場のフリーターは、バブル崩壊後「就職できない人」という負のイメージに転じた。
・社会の受け止めと就職支援の始まり
90年代後半以降、就職氷河期世代が増えたことでフリーターの数が急増。政治や企業も否定的な見方を強め、2000年代に就職支援が本格化した。
・現在の状況と今後の見通し
少子化も要因として、近年は人手不足により売り手市場に。労働参加できなかった育児中の女性や高齢者を含め、非正規の働き方が多様化。正社員でないことがネガティブに捉えられなくなることもあり、フリーターという言葉が使われなくなる可能性も指摘される。

中年フリーターの下流化加速と生活不安の実態
もう一つ、同年10月10日配信の<東洋経済オンライン>記事を参考に。
ここでも、非正規労働者の増加と中年フリーター問題を取り上げている。
これから深刻な問題として顕在化してくる「中年フリーター」の中心が、1990年代半ばから2000年代半ばに新卒として社会に出た「就職氷河期世代」の非正規労働者。
氷河期最初の世代はすでに40代に突入しており、年齢的に正社員に就くのが困難であるだけでなく、体力の衰えとともに働けなくなってくる。(現在は、50代に)
ずっと非正規で専門的なスキルも経験もない人になれば、なおさらハードルが高くなる。
そして、非正規の平均月収は約20万円と示し、中年フリーターの「下流化」の加速化を強調する。
低い社会保険加入率と気になる生活保護予備軍化
連合総研「非正規労働者の働き方・意識に関する実態調査」を用いてそれを実証。非正規が主たる稼ぎ手世帯のうち「貯蓄なし」が28.2%、「100万円未満」世帯26.6%と。
厚労省「就業形態の多様化に関する総合実態調査報告」では、非正規者の雇用保険加入率65.2%(正社員99.5%)、健康保険52.8%(同99.5%)、厚生年金51.0%(同99.5%)と、低い社会保険加入率実態を示している。
そのうえで、病気などで働けなくなり、社会保険などのセーフティネットからもこぼれ落ちると、最後に頼れるセーフティネットは生活保護しかない。
生活保護受給者は2015年7月時点で216万人と過去最多を更新。
それに匹敵する中年フリーター273万人が生活保護予備軍として存在する、と。
追い込まれる中年フリーターの実態
そして、こう分かりやすく論じている。
・親元で暮らしているから生計を維持できている人も少なくない。
・親の高齢化するとそれが難しくなるのは必至。
・それどころか親の介護が必要になってくる。
・また自らの老後にも不安を残す。
・国民年金のみの場合、満額で6.5万円。
・保険料未納の期間があると受け取る額は減る。
・老後は今以上に厳しい生活になってしまう。
非正規雇用者の低い賃金、不安定な雇用、教育訓練機会の乏しさ。
氷河期世代をはじめとした若いフリーター層に対して行われてきた就労支援も目立った成果が上がらないまま、中年フリーターたちは年齢を重ねてきた。
ますます苦しい立場に追い込まれていく中年フリーターをどうサポートするのか。
手を打たなければ事態が悪化していくことだけは確かだ。
前項で展開された、人手不足感からの雇用動向の改善傾向とそれを背景として「フリーター」がいなくなるのではという、多少、楽観的な見通し。
これに冷水を浴びせるような話に戻ってしまいました。
このレポートも10年前のものでしたが、現代であっても、同様の状況にあるミドルは、数多く存在することは違いません。

ワーク・アンド・ライフを立て直すためのミドルの非正規労働+副業
厳しい現実が種々レポートされていました。
では一体具体的にどうすることで中年フリーター地獄から脱却できるのか示されていませんでした。
これらの記事でレポートされた実態は、ほぼ10年前の話。
この時対象となったミドルは、10歳年齢を重ねています。
当時の状態の改善がみられていなければ、これからの一層の困難が予想されて当然。
新たにミドルに加わった方々の何割かもまた、非正規雇用の不安定・不安を同様に抱えていると思われます。
「就職氷河期世代」の就職難が、正規雇用化が進められているという一部の偏った動向とシンクロすることがほとんどなく、現在も続いています。
こうした方々にも、なんとか有効な副業を見出し、少しずつ生活安定化の道筋をつけるお手伝いができないか。
一層、その思いを強くしています。
ネット環境下の日常生活の確立を
この時、不可欠なのは、日常生活をネット環境の下で送っていること。
いきなり正規雇用をめざすこと、いきなり専門能力を高めて活用できる仕事を探すことは、誰にでもできることではないでしょう。
しかし、ネットを活用して、副業や求人・求職に関する情報に接することができる。情報を収集することができる。
ミドルであっても、それが可能ならば、行動を起こして頂きたいと思います。
先述したように、単純に年代・世代要因だけで論じることですべてをカバーすることはできません。
個々人の生活・仕事の状況に沿った議論と対策が必要であることを認識した上で、どのような副業が実際に可能か。
それらの生活・仕事の状況の違いには、どのようなものがあるのか。
その違いに応じて、どのような副業の機会があるか。
当サイトの課題の一つとしてしっかり認識し、情報提供と提案をできるよう、取り組んでいきたいと思います。

前回の記事に戻ります。
⇒ 新しい時代の働き方と人生設計|コロナ・災害・AI時代を生き抜く副業と起業の選択肢 – 副業起業.com
次回記事は、こちらです。
⇒ 子育てと仕事を両立|女性のための在宅ワーク・副業起業の可能性 – 副業起業.com






