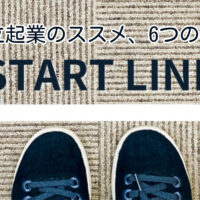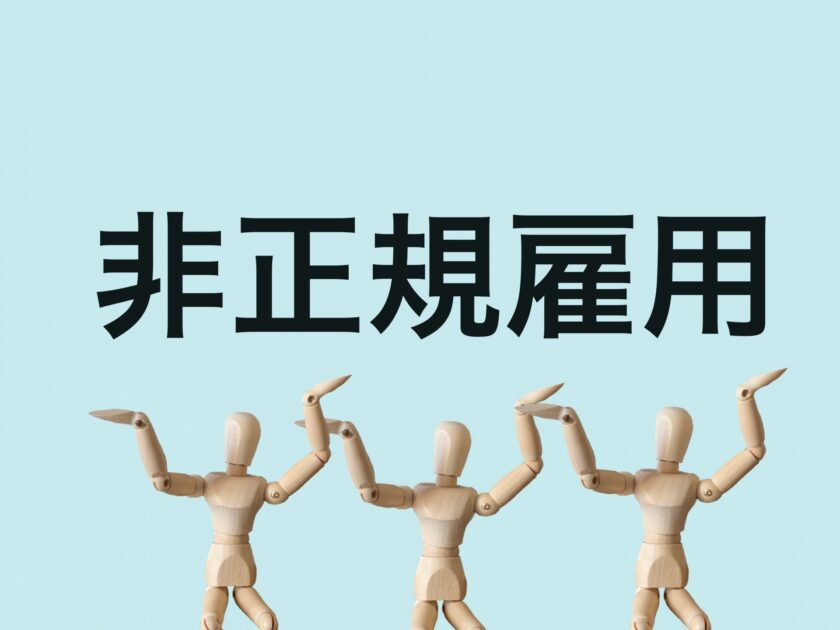副業市場は今どうなっている?統計に現れない働き方の実態と可能性
当サイトをリスタートしてから、以下の2つの記事を投稿しました。
第1回:新しい働き方を模索するあなたへ|副業・起業時代のWEB発信 – 副業起業.com
第2回:副業から起業へ!独立を目指すあなたに伝えたい6つの視点と行動指針 – 副業起業.com
今回は、少し視点を変え、1年前の日経記事を先ず紹介します。
そこから、副業市場の拡大を捉えて、サイトにおける副業重視について、お伝えします。
ページに広告が含まれる場合があります。
信頼できない政府統計
1年以上も前の情報で恐縮ですが、2024年3月31日付日経の<チャートは語る>という特集
「人手不足映せぬ政府統計 ハローワーク求職10ポイント減 曇る景気把握・政策」と題した記事が掲載されました。
記事の指摘の一つは、労働需給を示す政府統計が「ハローワーク」を主な情報源としていること。しかし、それが実態と大きく離れた指標を示しているというものです。
その論点を見ていきます。
ハローワーク指標の限界|求人倍率は人手不足を反映していない?
実態を示す数値を挙げると
1)日銀の2023年12月の短観(全国企業短期経済観測)調査では、雇用人員「過剰」から「不足」割合を引いた雇用判断DIはマイナス35と人手不足感が強く、19年3月調査以来の厳しい状況。
対して
2)厚労省23年10~12月期有効求人倍率(季節調整値)は、パートを含む一般で1.28倍で、4四半期連続低下し、16年1~3月期の1.3倍以来の低さ。(除、コロナウイルス禍期)
3)23年1~6月ハローワーク経由就労者割合は全体の約15%。
この厚労省データが政府統計というわけです。
日銀データでは人手不足、厚労省データは、そうではない。

副業・単発ワークが主流に|政府統計が見逃す働き方のリアル
日本の労働市場が大きく変化している中、政府統計が捉えきれない新たなトレンドが拡大しています。
最新の統計では、人手不足の実態が明確に示されず、求人数の目安である有効求人倍率が低下する一方。民間での求人・求職市場が躍進しています。
内閣府の調査によれば、正規の勤務だけでなく、単発の仕事や副業を希望する人々が増加。これによって労働市場のニーズが大きく変化しています。
特に若者や学生、社会人の副業ニーズが高まり、新たな働き方の多様性が生まれています。
それにとどまらず、物価高が大きく影響。年金収入だけでは不安を増している高齢者、生活費の補填を必要とした主婦の、短期的あるいは非正規の仕事や副業のニーズが増しているのです。
政府統計どうこうにかかわらず、副業市場は着実に成長しており、これからもその拡大が見込まれているのです。
冒頭紹介した状況は、当然、1年後の今も変わっていません。
確かに大企業を中心として、非正規雇用者の正規雇用への取り込みが進められてます。
しかし、一方でタイミーなどのアルバイト・単発雇用市場の拡大も話題になっています。このように、労働市場の多様化は、ハローワークのデータを公的データの主要基準として用いることが無意味であることを証明しています。
副業支援と起業への展望|当サイトが描くこれからの働き方
副業を推奨するする当サイトでは、こうした動向に注目。副業市場の成長を見逃さず、この市場の今後の見通しの強さと可能性をアピールします。
そのために、求人サイト情報の有効活用の提案を通じて、積極的な副業探しを支援します。
日経同記事で取り上げている時間単位で単発で働く「スポットワーク」や仲介アプリ「タイミー」。これらについても、後日取り上げたいと思っています。
AIが多くの仕事を奪うという予測もあります。しかしむしろ反対に、AIと関連する仕事も新たに産まれている状況あることにも関心をもっていきましょう。
もちろん、副業分野においてもAIは注目に値します。
副業は、経済の活性化に寄与する重要な要素ともなっています。
しかし、当サイトでは、基本的には、副業の多様性を一層拡充。個人個人の働き方、収入の獲得法の選択肢を増やすことを重視します。
加えて、副業をベースにしつつ、それがその後の起業に繋がることも期待したい。それにとどまらず、むしろ起業を念頭に置いて副業に取り組む方々が増えてくる。
自らの生き方・働き方をステップアップさせ、自己実現や多様な価値の創造に結び付けることに繋がれば。
それをも理想ともしているWEBサイトでありたい考えています。

前回記事に、戻ります。
⇒ 副業から起業へ!独立を目指すあなたに伝えたい6つの視点と行動指針 – 副業起業.com
次回の記事は、こちらから
⇒ 新しい時代の働き方と人生設計|コロナ・災害・AI時代を生き抜く副業と起業の選択肢 – 副業起業.com