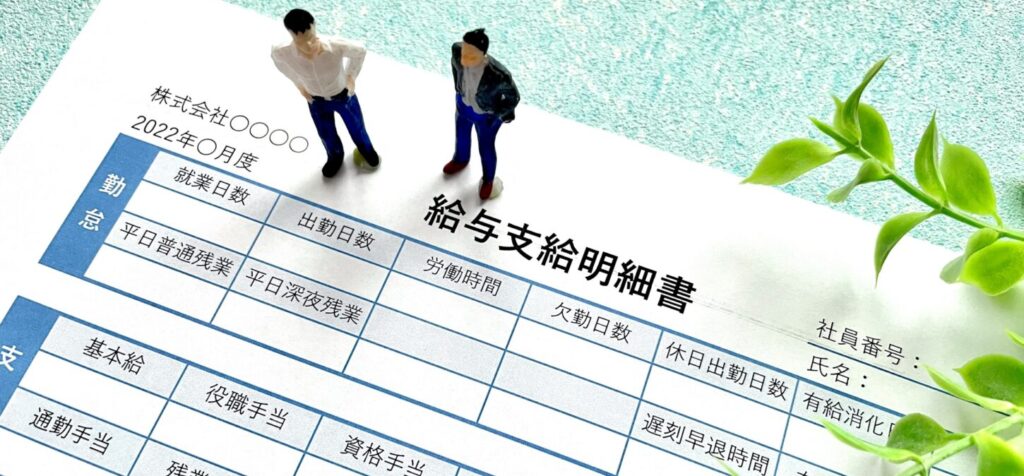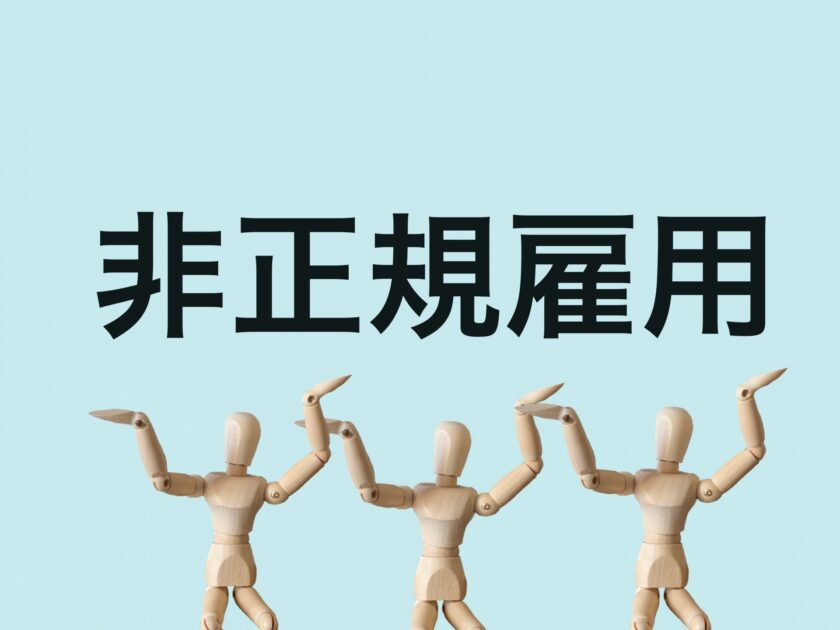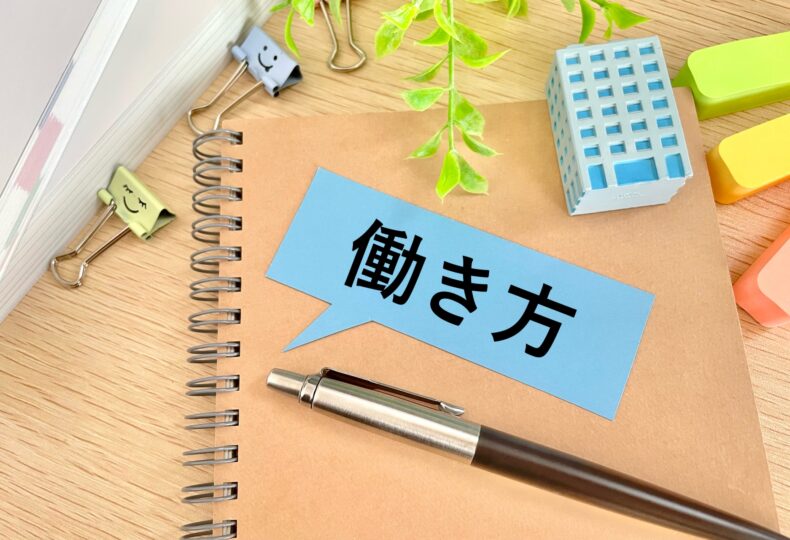
新しい時代の働き方と人生設計|コロナ・災害・AI時代を生き抜く副業と起業の選択肢
給与の妥当性を考える:あなたの仕事の価値は?
今もらっている給料は安いか不満か、それともそこそこ満足しているか。
コロナで、失業したり、非正規雇用で更新されなかったり、という状況では、それどころではない人も多いかもしれない。
でも、それだからこそ、今までもらっていた給料、今もらっている給料が安いか、妥当か、それとももらい過ぎか、考えてみる意味・意義はあると思う。
世間相場主義としての賃金
そもそも、会社に入って賃金を得る被用者という立場。
本来労働契約に基づいて、担当する仕事に見合った賃金・給料を予め決め、確認して就労しているわけだが、労使平等・対等でそれらの労働条件が決まっている実感はない。
会社が提示する賃金・雇用条件に初めから異議申し立てし、交渉して賃金・給料を上げてもらう、変える。
滅多にないことですね。
そんなことをやると、端から不採用!だ。
ジョブ型とメンバーシップ型の賃金制度の違いと共通点
ところで最近盛んに「ジョブ型」と呼んで、雇用や働き方、処遇の仕方に関して論じられる機会が多い。
では対する「メンバーシップ型」で決まっていた賃金制度と「ジョブ型」では、どこがどう違うのか。
私は、世間相場という要素が、どちらにも共通にあり、賃金・給料を決めていると考えています。
プロセスは違うが、結果的に大差ない、というのが私の感覚です。
メンバーシップ型といっても、毎日、経営者や管理者の都合で、仕事内容が変わるわけではない。
日々仕事は変わらないけれども、実際に携わっている仕事の賃金の世間相場とは大差ないのが大半だと。
時には、仕事が代わったときに、前の給料に比べて安い、とか、まれに、前の仕事に比べて楽だけれど、同じ給料でラッキー、ということもあるかもしれないが。
IT関係の仕事であれば、業界相場という世間相場があり、同じ企業内でも、職種の違いで賃金に違いが設定され始めているはず。
ジョブ型しかりで、ジョブの内容・職種に応じた世間相場があり、競争市場があり、それに応じた賃金・処遇が決められているわけだ。
そう結局、あなたの賃金は、世間相場で決まっていると、ほぼ言えると思います。
春闘をめぐる賃上げ事情
昨年2024年春闘は、大手企業の大幅な賃上げが実現しました。しかし、いきなり社員全員の能力と貢献度が上がったからの賃上げではないことは明らか。
基本的には、人材の確保・囲い込み、これからの採用をにらんだ経営戦略・人材戦略にあります。
まあ、それだけの余力が企業にあってこそのことで、多くの中小・零細企業には非現実的な話であろうことも明らかです。
2025年今春闘も同様の傾向ですが、特に初任給の引き上げ競争が顕著です。
楽だった年功型賃金制度、面倒だった業績主義・成果主義賃金
同じ仕事だが、個々人ごとに結果・成果があり、その違いが給料に反映されない。
あるいは、反対から見れば、一応職種・職務は同じだが、結果・貢献度が低くても賃金は変わらない。
年功型賃金は、そういう不平等があるので、成果・業績に応じて給料を変えるべきだ。
でないと社員のモティベーションが上がらず、士気に影響する。
経営サイドもその差・違いをどう処理し、処遇に反映させるか悩みは抱えてきた。
そんなことから成果主義賃金・業績主義賃金、成果主義人事制度・業績主義人事制度を導入する。
そういうトレンドもありましたし、今も継続している企業もあるかもしれません。
企業ごとの賃金政策への意識と取り組みの違い
しかし、思うに、年功型賃金・年功主義人事を完璧に行い、貢献度の違いをまったく賃金や人事処遇に反映させない企業などなかったのではと思います。
要は、程度問題か、経営者・管理職の恣意性・偏りなどに問題があった故のことと。
そういう組織で働かざるを得なかったのは、不運としかいいようがないかもしれません。
私だったら、交渉し、聞いてもらえなかったら転職している(かも)。
実は、別の面から見ると、年功型賃金は、運用管理が楽だった。
勤続年数や年齢が評価の物差しの軸だから、管理する方はやりやすい。
これが、一人ひとりの成果・業績の違いをしっかり見て、評価して給料に違いを出す、となると、仕事の基準・評価の基準をそれなりに明確に・客観的に設定する必要がある。
その基準を文章等で書き表して、提示して、説明するのも実は面倒だ。
場合によっては、書き出すこと自体が難しい。
結局、経営者や管理職の感覚、好き嫌いによる違いになってしまったりする。
しかし、ある程度の規模の企業なら、人事評価制度を導入して、年功的ではあっても、多少の成果主義・業績主義的賃金管理を行ってきていると思います。
他方、中小企業・零細企業などで働く人びとにとっては、年功制だ、成果主義だという議論そのものに縁がない。
なんとか事業をやっていく事が可能な賃金レベル、という独自の評価決定基準が効いている。
一応、世間相場を意識している上でのことだが。
ただし、自分の会社の利益、自身の報酬はしっかり確保したうえで従業員の賃金を決めている経営者もいないではないとも。
正規と非正規の賃金の違い
ここ数年、働き方改革との関係で、同一労働同一賃金であるべき、となんだかんだで法制化が進みつつある。
働き方改革との直接のつながりはなくて、要するに、非正規雇用の人の賃金が正規雇用の人と比べると不当に低いから、同じ仕事をしているのなら、同じ賃金にしなきゃいけない。
そういうことだ。
納得できることではある。
が、別の視点から見れば、正規雇用の人たちの賃金の決め方に問題があった、といえなくもない。
だから、同一労働同一賃金制は、正規雇用の人の賃金を下げる方向に働かせるかもしれない。
国や官庁は、企業において、非正規雇用から正規雇用への転換を図ろうとしている面もある。
しかし、不況などで労働市場が買い手市場の場合は、非正規雇用がしやすいので、賃金は上がらないし、好況で、なかなか雇用できない場合は、賃金は、自ずと上がっていく。
同一労働同一賃金の論理は、通用しない要素要因も種々あるわけだ。
今後は、労働人口の減少が進むので、非正規社員を正規社員に転換する動きが大手企業や人気職種において見られるだろうし、現実それが加速している。
しかし、コロナ禍は、経営サイドからすれば、非正規比率が高い方が、リスク管理には良いので、非正規比率はむしろ高まる要素要因は変わらず高いともいえる。
IT等一部の人気高報酬職種に限っては、非正規である程度自由に働くことができた方が、将来的に自分とそのスキルをより活かす働き方・生き方を実現する上で、プラスになるだろう。
給料を払えるだけの利益が出る経営、出ない経営
自分の賃金・給料を安いと感じるか、高いと感じるか。
いろいろ考えるのは自由だが、少し客観的に考える癖を付けておいたほうがよいと思います。
まず、雇用されている場合、雇用している事業が、ちゃんと賃金を払い続けてくれることができるかどうかが、最も基本の段階。
文句があっても、払えなければ、倒産して失業保険をもらって転職先を探すか、自分から見切りをして退職し、転職を考えるか。
なんとか、やっているような状況でも、ほぼ同様でしょう。
十分利益も出ており、もっと給料を上げても良さそうだが、上がらない、上げてもらえない。
こういう場合は、その企業・職場の事業経営の中で、自分の貢献度や仕事の価値を、評価してもらえるかどうかが課題に。
売上や粗利益(付加価値)の中で、粗利益がいくらあり、人件費がいくら、諸経費が幾らかかるか、など推測・推計してみることができればと思うのですが。
そのための経営基礎データが入手できるかどうかの問題もあるし、自分がその計算や評価ができる知識や能力の有無も関係してきます。
ただ、安い、面白くない、と不平不満・文句を言っているだけでは、前向きな話にはもっていけないんですね。
賃金はどうやって決まっているか、だれが決めているか、決め方は適切か
あなたの賃金・給料をだれが決めているか。
社長か、上司である課長か部長か、営業所長・工場長・センター長か。
決めるために何かデータを利用しているか、人事考課(評価)制度があってそれを用いているか、その際に上司と自分とのコミュニケーションがあるか。
決まった結果や理由・根拠について、説明があるかないか。
取り敢えず、給料の決定プロセスや決定方法・基準などが、合点がいかなくても文字や規定で用意されているかどうか、そこはまず確認しておくとよいと思います。
どれも決まっていなかったり知らされていない場合、それらについて尋ねたり調べたりする。
そういう基本的な点について、疑問や興味関心を持ち、何らかの行動を起こしてみることは、とても大切なことと思いますし、自分を変えるきっかけになるかもしれません。
ただし、自己中心的に陥らず、できることなら客観的に見、考えることが望ましいのですが。
競争力としての人材、勝ち残るための賃金と人材
会社などの事業は、持続させることを重要な目標の一つとしています。
まれに、自分が創った企業を、他に売却することを目標としている経営者がいるかもしれませんが、そうなっても事業は基本、継続します。
人材は、そのために存在するといえます。
持続することに、「成長する」ことが加わる。
競争企業が現れると、その競争に勝つための経営にも取り組む。
経営者の経営戦略に影響される面も大きいですが、人材の差がそこに現れることも多いといえます。
高いモティベーションを持つ良い人材を擁し、競争に勝つことができるよう貢献してもらうためには、高い賃金・給料を支払うことも必要になります。
新たに採用する場合ももちろんです。
そういう企業は、そのための能力がある、その価値がある人材に、やってもらいたい仕事に見合った賃金・給料を支払う契約をする。
それができる経営を行う自信があるか、成算があるかが重要な要素にもなります。
そうした企業・事業などに参加・参画できるチャンスを得ることを目指した働き方・生き方をしているかを考える機会があってもよいと思います。
そのために、どんな職種・技術・経験が必要か、も合わせて考える日々・時間・時期も持ちたいものです。
貴方がいなくても会社は回る、自分がいなくても会社は困らない
もし、即会社を辞めます、と申し出た時、きっと会社は、上司は、困って「辞めるな」と引き止めるだろう。
そう推測する、あるいは僅かながら期待もしているかもしれない。
確かに辞められると困ることのほうが多いかもしれない。
でも、一旦辞めたいと言ってきた人に対しての思い・感じ方は、そこから一気に変わる。
今すぐ辞められ、明日からもう来なくなる。
これは、確かに困る。
が、いつまでに、と期限が決まれば、会社・組織は何とでもなり、ちゃんと回っていく。
一旦辞めると申し出た人が、ずるずる長く働き続けるのは、歓迎されないもの。
ゴネ得みたいな形になって残るのも、双方にとって、気分・居心地がよくないだろう。
もし本当に必要で、いなくなっては本当に困る人材と見ていたならば、とうの昔に、期待や労働条件の変更など、何らかの申し出やコミュニケーションの機会をもっていたはず。
放っておかれたということは、そう見られていたということ。
それだけの会社・経営者だったとしてもよいと思うほうが正解かもしれません。
自分の仕事の価値はいくらか
さて、そうこうして、自分の賃金はいくらが適切か。
自分の仕事の価値は、いくらと値踏みできるか。
直接の営業に携わる仕事ならば、売上・粗利益、人件費・他諸経費など分解・分析して、自分の賃金の妥当性を大まかに評価確認できるかもしれない。
かもしれない、としたのは、本部経費など間接的にかかる諸費用が、上記の数値データに入っていないことが多いため。
というか、そういうレベルまで、組織別・部門別利益管理を行い、公開していない企業・職場がほとんどだから。
そこで、コロナ禍で余儀なくされた在宅勤務、リモートワークを体験した人は、その利益・コスト管理データを収集・試算してみることをお薦めしたい。
賃金のほか、在宅勤務で利用する事務・ネット環境、場所などの基礎コストを見積もり、自身の仕事から期待・想定できる収益を想定する。
そうではない仕事の場合も、自分の属する組織単位での収益・諸費用の合計を、自分ひとりに分割・分配し、賃金給料の絶対額や構成比が、適切かどうか客観的に評価する。
大まかでかまわないので、一度是非やってみては、と思います。
自分の給料を自分で決めることができる働き方
自分の賃金は、自分が決める。
それが望ましいやり方。
だが、企業など組織事業では、決定権は本人個人にはありません。
労働人口減少への対策は、高齢者雇用と女性雇用が、労働市場における最優先課題となっています。
そこでは、賃金に関する交渉云々よりも、働くサイドの希望する働く時間や日数などに焦点が当てられます。
雇用サイドは、契約期間や就労体制、賃金レベルなど、まず調整可能な雇用条件を重視します。
主に非正規雇用がその対象であることは明らかですね。
ただ高度専門職や、ジョブ型的な契約に基づく場合の賃金では、労使対等での交渉で決定する形が主になってくると思います。
この段階では、海外企業を含め、同種の職種のグローバル社会での世間相場情報も参考にしているでしょうし、働く方も、自分のスキルのレベルの評価や値踏みもある程度客観的にできるでしょう。
しかし、自分が思うものと相手が考えるものとが必ずしも一致するわけではないです。仮に労働契約を結び入社しても、ジョブに組み込まれた価値を創出し貢献することができなければ、契約は解除されるわけで、その主導権は自身にはありません。
自分の賃金を決める主導権を持つには
となると、究極の形としてあるのが、自分で稼いで、その稼ぎから諸経費を除いた利益から、自分で配分を決めて報酬として受け取ること。
このやり方で、自分の賃金、自分の価値を決めるのが最も合理的といえます。
但し、持続性・継続性がないと基準にはならないし、なにより安定性のない事業では、給料・報酬原資を確保すること自体不可能になってしまいます。
要するに、働くことは、働いて稼ぐことは、そう簡単なことではないわけです。
しかし、安定化し、継続可能になれば、自分で決めた賃金にだれも口を挟むことはできません。
一つの理想ではありますが、その基盤である働く場が、組織・チームとしてスタッフを抱えるようになれば。
その被用者の賃金・給料を決め、運用管理する立場になるので、経営者としての責任・力量が問われることになります。
その時、自分の給料・報酬を自分で決めた経験は、決してムダにはならないと思います。
だれかに自分の賃金給料を決められる。
自分で自分の賃金給料を決める。
雇用する人材の賃金給料を決める。
それぞれを経験し、それぞれの評価・判断・基準などについて考える機会を持つ。
それが、実は、多様な生き方や働き方を体現してきたことを意味すると考えます。
だれでもできることではないですが、その気になればだれもができることでもあります。
その経験・体験をするためには、日々いろいろ興味関心を持ち、調べ、身につけ、実践
してみる、ポジティブな生き方・働き方が望ましいのではないでしょうか。